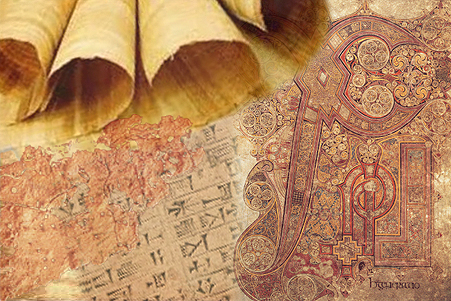私たち日本人は、日本建物の発祥とともに、木と紙と土で出来た家で暮らしてきました。木で骨組を作り、土で壁を塗り、室外と室内を障子で仕切り、室内は襖を立て部屋を区切りました。和紙を透かした自然の光は、室内をぼんやりと和やかに照らします。四季折々の庭の植物が映り込んだり、満月の夜は障子が青白く輝いたり、一日の間にも太陽の照らす色で障子の色が移り変わります。また、白く清潔な和紙の色と自然物の対比は、日本人が心癒やされる心境風景と言えるでしょう。古い文献の中にも、庭に積もった雪景色を障子越しに見るのが美しいと詠われています。障子越しに顔を見せず言葉を交わす、平安貴族の男女の奥ゆかしい姿を思い浮かべる方もいるでしょう。また、和紙は匂いも通す素材でもあるので、四季折々の自然の香りも楽しんだのではないでしょうか。現在は機械製造の障子紙がほとんどですが、それ以前は手透きの和紙が障子に使われていました。均等では無い、なにか混じり物がある和紙特有の透け感は、日本人の心を何か懐かしい気持ちに貫く素晴らしいものだと思います。障子越しに熱いお茶を一服、良いお時間ですね・・・